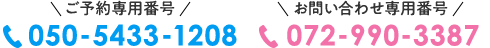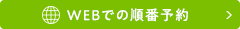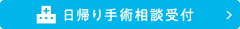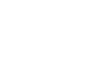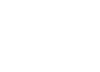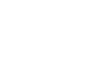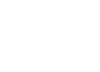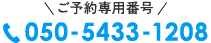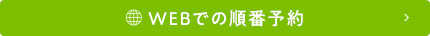副鼻腔炎 いま むかし
「はな垂れ小僧」という言葉があるように、昔は青鼻を垂らしている子供も多く、服で鼻を拭くため袖がカピカピになってしまう子供も多くいたように記憶しています。青鼻の原因の多くは感染からの修復過程の状態で、通常の免疫であれば自然治癒することが多いですが、長期間続く病態は持続的な細菌感染が存在し、3ヶ月以上続けば慢性副鼻腔炎でいわゆる「ちくのう症」となります。
最近では青鼻を垂らしている子供も随分見なくなりましたが、これは慢性副鼻腔炎が減ったからであると言われています。この傾向は成人にもあり、その背景には衛生状態が良くなったことや医療の充実によって重症化の予防がなされてきたことが大きいと思います。ただ、近年では従来の慢性副鼻腔炎に代わってアレルギーに起因し、喘息や鼻茸を合併しやすい好酸球性副鼻腔炎と呼ばれるものが増えてきており、衛生状態や医学の進歩に関わらず、アレルギー疾患が耳鼻科領域でも一昔前に比べると増加していることが関係していると言われています。
アレルギー疾患の増加の要因に関しては、諸説ある中で「衛生仮説」というものが近年注目されており、食を含めた生活環境の変化や衛生状態が良くなったことで逆にアレルギー反応が強く出てしまうというものです。やや専門的になりますが、アレルギーというのは白血球の一種であるTh1細胞とTh2細胞のバランスが崩れることで引き起こされるとされており、Th2細胞が増えるとアレルギー反応が強く出るとされております。Th1細胞は細菌感染の時に活躍するために、細菌感染の時はTh1細胞が活躍し、その反面Th2細胞が抑えられてアレルギー応答が出にくくなります。逆に言えば衛生状態が良くなり、細菌感染が抑えられた昨今の状況下ではTh1細胞の出番が少なく、Th2細胞が優位に立つためにそのバランスが崩れてアレルギー反応が強く出てしまうというわけです。
好酸球性副鼻腔炎もTh2細胞が関係するアレルギー主体の副鼻腔炎なのですが、喘息や鼻茸に加えて、中耳炎も合併しうる病態で、「はなづまり」「息苦しさ」「臭わない」「聞こえない」と四重苦で、重症の方は生活の質が大きく低下してしまいます。抗生剤やステロイド治療が基本治療となりますが効果は薄いことが多く、手術加療で鼻茸や病的粘膜の清掃を行えば鼻洗浄やステロイド点鼻薬等での管理である程度コントロールは可能ですが、術後の定期的なメンテナンスを怠るとまたすぐ鼻茸が再燃するという厄介な病態です。このような経緯からこの病気は2015年に国の指定難病となり、分子標的薬を代表とする新たな治療薬の開発も進んできております。
分子標的薬というと昨今では専ら癌治療方面での活躍が華々しいですが、簡単に言えば病気の原因や悪化因子となる分子(抗体やタンパクなど)を標的としてピンポイントに攻撃し、そこに関連する生体応答をブロックする治療です。好酸球性副鼻腔炎においてもアレルギーの免疫機構の中で特に炎症を強く引き起こすような抗体の存在が解明されていますので、その抗体を押さえ込むような分子標的薬がでてきております。同じアレルギー疾患であるアトピー性皮膚炎や喘息においては、重症例においてはすでに先駆的に使用されており、安全性も含めて良好な結果を得ております。新しい治療ですので適応は限られますが、当院でも使用可能としており難治性副鼻腔炎患者様の一筋の光となればと考えております。
耳鼻科遺伝子治療への道
Covid -19のワクチン接種が日本でも始まってきており、日本ではまず米ファイザー社製が導入されております。従来のワクチンは不活化ないし弱毒化したウィルスなどの病原体を体内に取り込む形でしたが、今回のワクチンはウィルスの遺伝情報を取り込む形です。さらに細かく言えば、ウィルス抗原を体内に作り出すために『DNAを介さない=人の遺伝子に組み込まれない』のがmRNA方式(米ファイザー社や米モデルナ社など)で、『DNAを介する=人の遺伝子に組み込まれる』のがアデノウィルスベクター方式(英アストラゼネカ社や米ジョンソンエンドジョンソン社など)となっております。
こう聞くとアデノウィルスベクターの方に副作用の懸念が多くなるのは仕方ないですが、既にウィルスベクターワクチンとしてエボラ出血熱へのワクチンとして存在しており、海外では承認されております。ウィルスベクターとは、ウィルスが人に感染した時にその遺伝子を人の遺伝子に組み込む特性を用いて作成されたもので、毒性や増殖能力が無いように改変されたウィルスを用いた『遺伝子の運び屋(ベクター)』という意味です。ウィルスベクターはその特性から、望む遺伝子を生体内に入れて病気を治すという遺伝子治療の分野でも、先天性疾患の治療(生まれつき欠損している遺伝子を入れる)や癌の治療(がん抑制遺伝子をがん細胞に入れる)などで実用化されています。ただ汎用化(一般的に広まる)には安全性の検証はまだ十分とは言えないようで、欧州に続き日本でもアストラゼネカ社製の接種が見送られたことを考えると、改良を含めもう少し汎用化までには時間がかかるかもしれません。
ただ、ウィルスベクターの汎用化が可能となればいわゆる遺伝子治療の分野がより身近になる可能性があります。様々な医療の分野で病気のメカニズムが遺伝子レベルで解明されつつある昨今、先天性疾患やがんのみならず、耳鼻科領域でも不治の病とされてきた病にも遺伝子治療のスポットライトが当たっております。
近年の報告では、加齢性難聴は内耳(聞こえの神経につながる部分)のGAP結合(内耳の環境を整える重要な分子構造)の崩壊がその一因と言われており、それにより聞こえの細胞がダメージを受けて難聴を引き起こすと言われております。このGAP結合の崩壊を修正・安定化するような遺伝子も明らかになってきており、それらを内耳の細胞に組み入れることで加齢性難聴の予防や改善につながる可能性が報告されております。
また臭いの領域でも、絨毛(臭いの神経細胞上にある小器官)が正常に形作られないことで起こる難治性嗅覚障害の一種において、絨毛の形成に関わるタンパク質(IFT88)コードする遺伝子を嗅覚の細胞に組み入れることで嗅覚機能の改善が認められたことが動物実験の上で報告されております。
安全性の問題は乗り越えたとしても、組み入れた遺伝子がずっと働き続けるのか等まだまだ乗り越えるべき壁はあるかと思いますが、歴史を顧みると、奇しくも技術革新は戦争など特殊な環境のもとで躍進してきました。コロナ禍という特殊な環境下で医療の技術革新がより進むことによって、諦めていた病気が癒える日が近づくかもしれません。
扁桃腺、とったら風邪をひきやすい?
厳しい寒さが続く中、例年この時期はインフルエンザの患者さんが多いのですが、今年はコロナの影響でマスクや手指消毒が習慣化している影響でしょうか、インフルエンザは大幅に減っている現状です。インフルエンザやコロナなどはウィルスの感染ですが、同じ発熱や喉が痛くなる症状をもたらす細菌の感染に扁桃炎があります。口の奥の両側にある扁桃腺の中で細菌が増殖する病気ですが、悪化すると細菌が喉の深部に入り、さらに重症化すると血液中に細菌が入り込み致死的な病態になりうることもあります。
抗生剤の恩恵がある現代では扁桃炎で重症となることは稀になりましたが、抗生剤が行き渡る以前は重症の扁桃炎の治療には外科的切除が施されていました。その歴史は古く、紀元前1世紀の古代ローマ時代には扁桃腺手術の詳細が記されております。日本でも20世紀初頭から半ば過ぎまでは、子供は扁桃腺が大きい(扁桃肥大)だけでとった方がよいとされていた時代があり、耳鼻科外来で椅子に座ったまま扁桃腺をとる手術が日常的に行われており、高齢者の方で幼少期にその経験のある方は苦い思い出として残っているかもしれません。扁桃腺は局所麻酔手術だと、咽頭反射(えずき)のコントロールが難しい上に圧迫止血が十分に行えないために安全な手術を行うことが難しく、現在では全身麻酔下での手術が一般的となっております。
子供の扁桃腺手術の適応ついては現時点で基準は大きく2つあり、1つは繰り返す習慣性の扁桃炎があること、もう1つは扁桃肥大による重症の睡眠時無呼吸があることとなっております。習慣性の扁桃炎に関しては、我が国では年3−4回繰り返す扁桃炎とやや幅を持った感じで言われておりますが、米国ではより細かく規定されており、定期的な改訂も行われ、2019年の改訂版では手術の前にもう少し経過観察を要する方向へと切り替わってきております。さらに、同じ頃に扁桃腺免疫の常識に一石を投じる報告がオーストラリア・デンマーク・米国の共同研究から発表されており、その内容は、子供の時に扁桃腺をとったグループがとっていないグループに比べて上気道感染(いわゆる風邪)にかかるリスクが約3倍増加するというものです。長年、扁桃腺は子供の頃にとってもその後の免疫機能に異常をきたさないとされておりましたが、術後長期間にわたって手術の影響を追ったデータが存在しておりませんでした。今回この報告が初の長期データ(術後10年から30年の経過を追ったデータ)をまとめたものとなり、長い期間で見た場合、扁桃腺をとることが将来の免疫機能の低下に繋がる可能性が示されたということになります。本当にその子供の扁桃炎が習慣的なもので治りにくいものなのか、その見極めをもう少し慎重にすべきであるということになります。
もう1つの手術適応である扁桃肥大に関して、よく保護者の方から「どうして起こるのか?」という質問をお受けします。経験的に両親からの遺伝の可能性は言われてきておりますが、最近の知見ではモラキセラ・カタラーリスという細菌が扁桃肥大に寄与していること、特定の遺伝子(Beta-defesin 1)が扁桃肥大に関与している報告があがっております。総じて、扁桃肥大は遺伝的な側面はあるものの、適切な消炎が大切と考えますので、扁桃腺内に細菌感染の基地(コロニー)を作らせないために、炎症を長引かせないよう早めの対応が要です。
耳鳴(じめい)の理
人は太古の昔より耳鳴りに悩まされており、最古の記載は紀元前1500年頃のパピルスに書かれた古代エジプトの医書に見られるとも言われております。当時は耳鳴りを有する耳は「魔女に取り憑かれた耳」とも言われており、葦の茎を用いて直接耳の中に樹液・樹脂・ハーブなどを混ぜた特性オイルを注入して治療されていたようです(かなり痛そうです・・)。またラテン語の繰り返す音を意味する「tinnire」が現在の耳鳴り(tinnitus)の語源という説もあるように、いかに人類がこの繰り返す耳の中で鳴る音に悩まされてきたかということですが、現在に至っても耳鳴りを完全に消すことは難しく、「耳鳴りの治療薬を開発したらノーベル賞クラス」と言われるほど多くの人々はこの耳鳴りに苦しんでおられます。
腫瘍や炎症などのケースを除いて多くの耳鳴りは難聴を伴っており、鼓膜の奥の内耳という場所に存在する音受容器や脳の聴覚を処理する聴覚野において、その刺激が無くなることで耳鳴りは起こると言われています。一般的に、年齢による難聴の進行や騒音による難聴は内耳の音受容器の細胞が変性・消失することよって起こりますが、内耳で障害が起こると当然脳にも刺激が届かなくなるわけで、その際に刺激を失った脳の聴覚野にある神経細胞が刺激を求めて非聴覚野へ神経が伸びていくことが耳鳴りと深く関係していることが最近の研究で分かってきております。
このメカニズムを逆にとれば、脳の聴覚領域に入ってこなくなった音刺激を、再度入れてあげれば、脳の神経細胞は刺激を求めて非聴覚野へ神経を伸ばさないようになるというわけです。事実、補聴器やTRT(Tinnitus Retraining Therapy:特定の音のみを与え続けることに特化した耳鳴り順応療法)、さらには人工内耳といった失われた音を取り戻す人工聴器など耳に音を入れる状況が、耳鳴りを軽減したという報告が多数あります。米国の耳鼻咽喉科学会が長年の耳鳴り治療の莫大なデータをまとめ、2014年に治療に対する一定の評価を示しており、そこでも難聴を伴う耳鳴りに対しては補聴器は推奨治療として、TRTを含む音を入れる「音響療法」は一定の効果のある治療として評価されております。補聴器や「音響療法」の他には精神・心療内科領域の治療であるカウンセリングや耳鳴りへの注意をそらすトレーニングを含む「認知行動療法」も推奨治療とされており、「生活に支障が出る状況」を「生活に支障が出ない状況」にするという意味でも効果は高いとされております。
その他の治療、いわゆる内服を含む薬物療法やマッサージなどは残念ながら科学的根拠に乏しい耳鳴りの治療ということになります。ただ実際には、それらが効いたという方も少ないながらもおられますので一概に無効とは言えないのですが、近年の研究でそれらのメカニズムもだんだん明らかになってきています。一例を挙げれば、難聴を伴わない耳鳴りの一つに体性耳鳴(皮膚感覚並びに顎関節や首の筋肉の感覚といった体性感覚の不調による耳鳴り)と呼ばれるものがあり、脳幹(脳の中枢)にある体性感覚のコントロールセンターと聴覚の伝導を中継する部分との間で新たな神経の伸長が出来上がってしまうことで、耳鳴りが発生するメカニズムが言われてきております。こういうケースでは顎関節や頸部のマッサージで体性感覚のコントロールセンターに刺激を与えることが耳鳴りの抑制に有効であるという報告も上がってきており、マッサージも病態によっては有効といえる可能性を示しております。
ウィルス感染による嗅覚障害
世界的な感染の広がりを見せている新型コロナウィルス感染ですが、収束への糸口が見出せるように一刻も早い治療法の確立が待たれる現状です。治療法が確立していない状況では、できるだけ感染拡大を防止することが重要であり、当院でも可能な限り感染予防に取り組んで日々の診療を継続しております。
新型コロナウィルスの初期症状は一般的な風邪症状を呈しますが、中でも嗅覚障害(味覚障害)を呈することが多いことが報告されてきております。そういう背景もあり、嗅覚障害や味覚障害が生じた時は新型コロナウィルス感染の可能性も否定できないために、まずは7日間程度の自宅での隔離を行い、発熱・倦怠感・咳など追加の症状が出現しないかを観察していくことが感染拡大を抑える上で重要とされております。ただ、嗅覚障害の多くは副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎に加えて一般的な風邪のウィルス(ライノウィルスやインフルエンザウィルスなど200種類以上)によって引き起こされますので、嗅覚障害を生じたことが新型コロナウィルス感染をすぐに意味するわけではありません。とは言うものの、その可能性はありますので落ち着いて慎重に追加症状の有無をしっかり見ていかなければなりません。
嗅覚を司る嗅細胞が存在するのは嗅上皮という部位で、鼻の奥深いところ(眉間の奥)にあり、臭いの分子が空気の流れに乗って嗅細胞に届かないと嗅覚障害をきたします。多くの嗅覚障害はこの病態、すなわち鼻の粘膜が腫れて嗅細胞までに空気の流れが届かない状態(副鼻腔炎・アレルギー性鼻炎・風邪)で起こり、この状態を呼吸性嗅覚障害といいます。それとは別に、嗅細胞そのものがやられてしまって臭いの分子が嗅細胞に届いてもその奥の神経(嗅神経)に刺激が行かないという病態もあり、これを神経性嗅覚障害といいます。神経性嗅覚障害は主にウィルスが嗅細胞に直接感染することや、ウィルスに対する体の免疫応答によって嗅細胞が障害されることによって起こるといわれております。
神経性嗅覚障害として多いのは感冒罹患後嗅覚障害と言われるもので、いわゆるインフルエンザ等の風邪症状で鼻が詰まっているので臭いがしないと思っていると、風邪症状が落ち着いて鼻が通り出しても臭いがしない状態が続くというものです。ウィルスによる神経毒性により嗅神経が障害されてしまうのではないかと言われており、新型コロナウィルスによる嗅覚障害もこの神経性嗅覚障害の一つと考えられております。
嗅細胞は嗅神経末端にあり、嗅神経は脳神経の一種です。脳神経の末端は通常一旦傷つくと元に戻らない繊細でナイーブなものなのですが、その中にあって嗅神経末端である嗅細胞は再生を繰り返すと言う特異な能力を持っております。故に神経性嗅覚障害になったからといって治らないと言うわけではなく、その半数位以上の方は完治もしくは改善に至るとされております。ただ、改善に至るには一年以上かかるケースも珍しくなく、再生された神経細胞がその機能を取り戻すためにはある程度時間を要するということだと思います。
ただ残念ながら、中には治療効果なく臭いが戻らないこともあります。しかし、昨今の再生医療の現場においては、元来再生しうる嗅細胞をターゲットとした研究も多く、iPS細胞などの登場で更なる知見が深まっている領域ではあります。そう遠くない未来に嗅覚障害克服の日が来ることを願いつつ、ただ、まずは新型コロナウィルス感染の収束がそう遠くない日に来ることを切に思います。
花粉症とアレルギーコンポーネント
1月に入るとスギ花粉の飛散がぼつぼつ始まります。約4人に1人と国民病とも言われるスギ花粉症ですが、これは世界的にみると日本特有で、戦中の軍需利用で大量の木材を消費したために戦後にスギ植林を日本各地で行ったことがその一因と言われております。
鼻汁を訴える患者さんにアレルギー性鼻炎と言われたことがあるかを聞くことがありますが、「花粉症は言われたことがあるけどもアレルギー性鼻炎と言われたことはありません」という答えが返ってくることが時にあります。花粉症自体はアレルギー性鼻炎の一つで<季節性アレルギー性鼻炎>と言われており、それに対してハウスダストやダニなど1年を通して反応する鼻アレルギーを<通年性アレルギー性鼻炎>と言います。
アレルギー性鼻炎の診断は採血で行うのですが、アレルギー自体は抗原と抗体が反応して起こる免疫反応(抗原抗体反応)ですので、それぞれの鼻アレルギーをきたし得る抗原(ハウスダストやダニ、春のスギや秋のブタクサなど)に対して自身がIgE(アレルギーに関係する抗体)をどの程度持っているのかで重症度の目安となります。いわゆるRIST・RAST検査と言われるもので、臨床の現場では約40年前から取り入れられております。RISTとは総合的な血中のIgEを測定するもので、アレルギー反応がどの程度体の中で起こっているのかを示します。もう一方のRASTとは各々の抗原に対してどれだけアレルギー反応が出ているのか(IgEが高いのか)を示します。
近年はさらに抗原の中でもよりミクロなレベル、すなわちIgEが結合するタンパク部分の解析が進んできており、IgEが直接結合する部分(タンパク)をアレルゲンコンポーネントといいコンポーネントでアレルギー反応を捉えていく時代になろうとしております。言い換えれば食物アレルギーやアレルギー性鼻炎はそれぞれの食物や花粉に対して起こっているというのはやや粗い理解であり、それぞれの食物や花粉がもつもっと詳細なコンポーネントの部分でアレルギー反応を理解していこうというものです。この理解が医療の場で応用されているのは主に食物アレルギーの分野ですが、耳鼻科領域でも近年は「花粉–食物アレルギー症候群(PFAS)」や「口腔アレルギー症候群(OAS)」と言う概念で取り上げられております。
PFASやOASの代表例の一つに春に花粉を飛散するハンノキ(カバノキ属)にアレルギーを持つ人がリンゴを食べると口のイガイガをはじめとしてアレルギー症状を引き起こすという状態があり、これはハンノキのもつコンポーネントとリンゴの持つコンポーネントが構造として似ているため、ハンノキのコンポーネントに反応するIgEがリンゴのコンポーネントにも結合してアレルギー症状が出てしまうためと言われております。ただこのリンゴのコンポーネントは熱で変性してしまいますのでアップルパイであればアレルギー症状は出ないということも分かっております。
これらのコンポーネントに関する新たな知見がどんどん明らかにされていくことで病態の新たな解明や治療の多様化に繋がる可能性が言われており、当院でも春にアレルギーを有する方のアレルギー検査(RAST検査)にはハンノキ花粉を加えております。今回はやや専門的な話になってしまいましたが、気になる方は一度ご相談ください。
インフルエンザワクチンの進化
「インフルエンザワクチン打ったのに家族全員かかったわ・・ホンマに意味あるんかな・・」こういう声も未だ聞かれる現状ですが、そんな中でも毎年この季節になると各病院や診療所でインフルエンザワクチン接種が始まります。僕が子供の頃はワクチン接種が学校で義務化されており、皆一列に並んで嫌々ながらワクチンを打たれていたものでした。詳しくは昭和51年から学童へのワクチン接種が義務化され、その後「ワクチンの効果」が疑問視され平成に入った頃には義務化から準義務化となりました。さらに平成6年には学校での集団接種はなくなり、それ以降は事実上の任意接種となり接種件数は激減する経緯を辿るのですが、この「ワクチンの効果」が疑問視された最大の理由は冒頭の声のように打ったのにインフルエンザにかかるという事実が、ワクチンが効いてないという「誤解」を与えてしまったせいだと言われております。
これがなぜ「誤解」かと言いますと、現状のワクチンはインフルエンザにかかった後の症状を和らげる為のものであり、決して予防では無いからなのです。ただ、症状を和らげる効果は科学的にも検討されており、平成6年以降に学童の集団接種が廃止された後に高齢者のインフルエンザ関連死が増えたこともインフルエンザワクチンの効果(症状の重症化を避けるという点)を裏付ける歴史的事実とされております。
では、なぜインフルエンザワクチンが感染予防ではなく症状緩和にしか効果がないかということですが、それは現状のワクチンが不活化ワクチンであり「血中の免疫」を上げる働き、いわゆる血中のインフルエンザ抗体を強化する効果しかないという点です。インフルエンザが感染するのはくしゃみや接触によるもので、ウィルスが目鼻や口の粘膜に侵入することで感染していきます。その後感染が成立すると遅れてインフルエンザ抗体が産生されて「血中の免疫」が作られていくのですが、感染の予防効果を目指すのであれば、感染が成立する前の粘膜の部分でウィルスをやっつけるいわゆる「粘膜の免疫」の強化が必要です。加えてこの「粘膜の免疫」はインフルエンザの型(A型・B型など)を超えて効果があるとされている点も従来の不活化ワクチンよりも優れているとされています。
近年、この「粘膜の免疫」を上げるインフルエンザワクチンの開発も進んでいます。いわゆる経鼻ワクチンと言われるもので、鼻から生ワクチンを散布して擬似感染状態を作り出して免疫を誘導するメカニズムです。日本では未承認であるものの欧州や米国では先行使用されており、従来の不活化ワクチンよりもメカニズムの上では効果は高いとされ、専らその感染予防効果に関しては一目置かれております。ただし、日本で未承認である理由として免疫反応が弱い高齢者にはうまく免疫がつかずに効果がないとされている点や生ワクチンであるがゆえに保存状態でその効果に変動があり、中々うまく免疫が獲得できないという報告も多くその効果が疑問視されている点が挙げられます。ただ、医学は日進月歩ですので感染メカニズムをさらに詳細に解明していくことで、免疫反応が弱い高齢者も含めしっかり免疫が獲得できるような経鼻(経口)ワクチンの開発が進められている現状です。
「インフルエンザワクチンをしたから、我が家はインフルエンザ知らず」そんな時代も近いかもしれません。
突発性難聴とステロイド治療
「朝起きたら突然の耳鳴りや耳の違和感を覚える。そのうち治るだろうとそのまま様子を見ていたが治らない。」これは一般的によく見る突発性難聴の患者さんのエピソードです。めまいを伴わないために日常生活が進まないほどの支障が無く、来院が遅れがちになりますが、最近はインターネットやSNSでご自身や周囲の方が比較的早く調べて情報を得るので一昔前ほど手遅れという状況は少なくなってきている印象です。
手遅れって?ということですが、治療開始の時期は早いに越したことはなく、1週間以内とくに48時間以内が望ましいと言われております。原因不明とされている突発性難聴ですが、ウィルス感染・循環障害・免疫異常の混在により聞こえ(の振動)を感知する感覚細胞に障害が生じて起こると言われております。この聞こえを感知する感覚細胞は生まれた時から数が決まっており、困ったことに一度その機能を失うと再生しません、ですのでその機能を失う前に少しでも早く治療をというのがこの病気の治療の難しいところです。
突発性難聴の治療においては炎症や免疫を抑える作用のあるステロイド治療が広く行われてきております。原因不明なのに?と思われるでしょうが、これは難聴も合併する免疫関係の全身の病気(自己免疫疾患)で治療の一環としてステロイド治療を行なった時に難聴も同時に改善したことに由来します。それ以降わが国では突発性難聴を含む原因不明の難聴には経験的にステロイド治療がよく行われておりますが、近年の研究からこの病態の解明も進みつつあり、ステロイド治療がいかに分子・遺伝子レベルで繊細な聞こえを感知する細胞を保護するか、機能を取り戻すことに役立っているかが明らかになってきておりこの治療の有効性を後押しするものとなっております。
ステロイド治療と聞くと、特に年配の方々は副作用を心配される方も多い印象を持ちます。乱用による副作用が多く出た時代のイメージかと思いますが、現在はゴールを決めて短期間で使用することで副作用を出さないように使用するというのが一般的です。特に突発性難聴の治療でのステロイド使用は通常は1週間程度という非常に短期間での使用であり、安全性の面では概ね問題ないとされております。ただ、血糖をあげる作用が強く出ますので重度の糖尿病の方は、ステロイド使用期間中はインシュリンによる血糖コントロールをしなければならず、入院加療が必要ということになります。
外来通院でのステロイド治療は飲み薬か点滴かを重症度等も考え患者さんと相談して決めていきますが、どうしても全身ステロイド治療に抵抗があるという方には鼓室内注入という選択肢もあります。鼓膜の奥の中耳という空間にステロイドを満たし、さらにその奥の繊細な感覚細胞がある内耳にステロイドを浸透させるというやり方ですが、最近の報告では全身投与と同等の効果も認めており、ステロイドが全身に及ぼす影響はほぼありません。鼓室内注入は当クリニックでも外来で行っており、注入後は10-20分間横になったのちに帰宅となります。いずれにせよ突発性難聴の治療にはゴールデンタイムがあり、感覚細胞が細胞死に至ってしまうとその機能を取り戻すことは難しくなってしまいます。耳の異変に気付いた時は早めの受診を。
たかが鼻づまり、されど鼻づまり
自然に口呼吸をする哺乳類は人間だけと言われております。喋る能力を獲得したがゆえに口呼吸になったという説もありますが、本来は人間も他の哺乳類と同じく鼻呼吸をするのが自然な形です。なぜ口呼吸になってしまうかというと本来自然な形である鼻呼吸が難しくなるからであり、その原因は両鼻を塞いでしまう病態です。大人の場合、その多くはアレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎(ちくのう)といった炎症によるものや鼻中隔湾曲症といった鼻の真ん中の柱が左右に大きく曲がってしまっている構造的な問題による原因であることが多く、子供の場合はアデノイド増殖症といった鼻の奥の扁桃腺が大きくなり鼻の奥で空気の通り道を塞いでしまっていることが多いです。
鼻づまりの結果引き起こされる口呼吸ですが、短期間であればそれほど問題はありませんが慢性的となるようであれば口腔乾燥や睡眠中の無呼吸を引き起こしてしまいます。口腔乾燥はさらには慢性的な喉の炎症、高齢者であれば誤嚥性の肺炎に繋がっていくリスクであり、今や無呼吸は高血圧を代表とする循環器疾患や、認知症を含めた脳血管障害に繋がっていくリスクであると言われております。鼻づまりはさらには口呼吸のみならず耳とも繋がっておりますので特に子供にみるアデノイド肥大においては滲出性中耳炎という小児難聴の代表格を引き起こしてしまうことになってしまいます。
鼻づまりを劇的に改善させる手段の一つに手術があり、そのことで得られる効果の報告は上に述べたごとく様々ではありますが、最近の研究報告から成人と小児それぞれを対象にしたものを二つ紹介します。
一つは鼻中隔湾曲症による鼻づまりがある成人患者さんに対して鼻中隔矯正術を行ったことに関連する報告で、その結果、鼻づまりの改善により血中のLDLコレステロールが有意に手術の前と後で変化し改善したというものです。LDLコレステロールは動脈硬化の形成を担っているため、鼻づまりの改善が循環器病態の改善につながり、ひいては動脈硬化の改善につながる可能性についてこの報告は述べております。
もう一つは小児のアデノイド・扁桃腺切除からの報告ですが、口呼吸となっていた小児に対してアデノイドと扁桃腺の切除を行い、鼻呼吸をメインに変えることにより明らかに肺動脈圧が低下したという報告です。この事実は大人において、睡眠時無呼吸が高血圧の原因となることはすでに言われておりますが、その治療のCPAP(睡眠中に鼻に装着したマスクから空気を送り込む治療)時に鼻が通っていなければ十分効果が発揮できないということの裏付けにもなると考えます。
計測機器等の発達の影響もあり、鼻呼吸が生理的にいかに大事であるかが明らかになっていく昨今です。いい鼻で健康な人生を送りましょう!
耳鼻科と繰り返す頭痛
梅雨の時期に入ってきて気圧が不安定な季節を迎えることになりました。これも四季の移り変わりの一環として「もののあはれ」と感じることができればいいのですが、この時期に耳鼻科では頭痛を訴える患者さんが増える印象を受けます。耳鼻科的な頭痛としては副鼻腔炎や中耳炎に伴うものが多く知られておりますが、そういった炎症を起こす病気もなく、脳神経がやられている症状もない場合はよく片頭痛・筋緊張性頭痛という病名で鎮痛薬等が出されるというケースは少なくありません。
近年、このような気圧の変化に伴う一連の頭痛やだるさ等、自律神経失調のような症状を示す病気を気象病という概念で捉えられつつあります。その原因は耳の奥の内耳といわれるリンパ液で満たされている場所にある圧を感知するセンサーが問題であると言われておりますが、詳細なメカニズムはまだ分かっておりません。実は耳鼻科でも同じような内耳の病気でメニエール病というのがあり、内耳内のリンパ圧が上がることで内耳内に存在する聞こえを感知する細胞や平衡を感知する細胞が圧によるダメージを受けるために、難聴(耳がつまった感じ)や耳鳴りならびにめまいといった症状が出る病態です。メニエール病は、その病気が提唱されてから150年以上経ちますが未だにその詳しい原因は不明です。ただ国内外の多くの研究者の努力のもと、ストレスがかかる時に発せられるホルモン(ストレスホルモンの一種で抗利尿ホルモン)により体内で水分が貯まる傾向になり、結果的に内リンパの水ぶくれ(水腫)をきたしてしまうということは分かってきております。体内での水の代謝を促すために積極的な水分摂取が効を奏することも言われており(正確には水分摂取により抗利尿ホルモンが出なくなり、結果的に内耳の水ぶくれが引いていく)、利尿剤と並ぶ効果的な治療と考えております。
このメニエール病といわゆる気象病との関連性については、重なる共通点も多いことから共通の病態がある可能性もあります。さらにメニエール病と同じような病態を示す片頭痛の病気もあり、前庭性片頭痛として名前も存在し診断するための基準もできています。最近の海外からの報告ではメニエール病の方の4割に前庭性片頭痛の合併の報告も上がってきております。繰り返す頭痛の裏に内耳の水ぶくれが隠れている可能性もありますが、逆に内耳の水ぶくれと頭痛の関連性が明らかになれば、内耳の病気をコントロールすることで頭痛のコントロールができる可能性もあり、今後の知見の結果が待たれるところです。