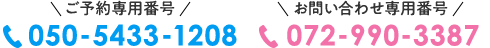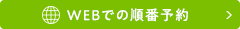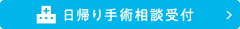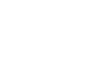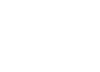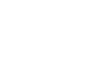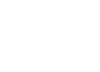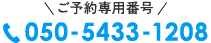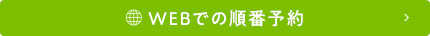鼻すすりません かむまでは
インフルエンザ感染が過去にないくらいの勢いで猛威を振るっています。インフルエンザは、ヘルペスなどのいわゆる風邪ウィルスに比べると発熱などの症状が強く出るため、一般の風邪ウィルスとは一線を画した厄介なウィルスとして取り扱われます。特にインフルエンザ脳症は小児の重篤な合併症としてよくクローズアップされますが、小児におけるウィルス性脳症の原因はヘルペスもインフルエンザと同等の割合であり、インフルエンザのみならずただの風邪も軽んじること勿れということになります。基本的にインフルエンザを含めたウィルス感染は自己の免疫で治します。ワクチン接種も自己の免疫を強化する手段の一つですが、インフルエンザにはウィルスの増殖を抑えるタミフル®︎やリレンザ®︎などの抗ウィルス薬があり、発症48時間以内の投薬で発熱期間を約24時間短縮する効果があるとされています。しんどい期間が1日短縮されるのは非常にありがたいことですが、抗ウィルス薬なしで治した場合は強い免疫を獲得できるため、抗ウィルス薬を用いないことはデメリットばかりではありません。
ウィルス感染で問題となるのはその合併症であり、罹患期間が長いと拗れてしまう可能性が高くなるので注意しなければなりません。前述のウィルス性脳症は重篤な合併症の一つですが頻度は高くなく(小児で約1万人に1人:0.01%)、頻度が高い、いわゆる拗れやすい病態は細菌感染の合併で、中耳炎・副鼻腔炎などの上気道病変、次いで肺炎などの下気道病変が挙げられます。特に小児では中耳炎や副鼻腔炎に発展しやすく、近年の大規模再調査の一報でもその合併率は中耳炎で37%、副鼻腔炎で8%とされており、いかに多くの子どもが風邪をひくと中耳炎や副鼻腔炎になるかということが伺えます。
中耳炎や副鼻腔炎が子供に多い原因は構造の問題であり、ウィルス感染による炎症で粘膜の自浄作用が低下し細菌が増殖するのですが、小児は構造が未熟ゆえ鼻と中耳や副鼻腔の行き来がしやすいので容易に鼻の細菌が広がりやすいということです。構造以外にも、もう一つ中耳や副鼻腔の陰圧というのもその広がりやすさに深く関係しています。ゆえに小児に比べ構造が広い大人でも、風邪ひき中に中耳や副鼻腔を陰圧にすると拗れてしまいます。そして、その陰圧を作りだす最たる要因は鼻すすりの繰り返しと言われています。
「風邪を引いた時は鼻をすすった方がいい」という意見も確かに見聞きしたことはあります。その理由として、鼻かみの圧で鼻の細菌が中耳や副鼻腔に到達する点、鼻をすすって飲み込むことで細菌が胃酸で処理できる点などが挙げられています。ただ、事実として耳管開放症(耳と鼻を繋ぐ管である耳管が開き、耳の中と鼻の中の圧が行き来自由)の方は鼻をすすった時に鼓膜が凹み、鼻をかんだ時に鼓膜が膨らみます。これの意味するところは、副鼻腔などの鼻に通じる空洞は鼻すすりで陰圧となり鼻かみで陽圧になるということです。加えて、持続的な鼻すすりが中耳の長期の陰圧をもたらし鼓膜の凹みや癒着の原因になることもわかっています。これらから、風邪引き時の持続的な鼻すすりで中耳や副鼻腔は陰圧となり、鼻の細菌が中耳や副鼻腔に引っ張り込まれることで中耳炎や副鼻腔炎が起こりやすくなると思われます。確かに、鼻かみの圧で鼻の細菌が一時的に中耳や副鼻腔に到達することはあると思いますが、鼻かみ後は副鼻腔や中耳は陽圧に傾きますので、よほど強くそして連続的にかまない限りその後細菌は鼻の中に押し戻されると思われます。
鼻はゆっくり片方ずつ、適切(強すぎず弱すぎず)にかむ。鼻はすすり続けず、すすりすぎた後は鼻かみを忘れずに。風邪をひいた時は実践してみてください。
めまい・耳鳴りは台風のせい?
暑い夏が終わりを告げようとしておりますが、ここ数年は最高気温を更新したりゲリラ豪雨が多発したりと日本の亜熱帯化を心配するような気候です。亜熱帯化が進んだ場合は台風の増加が予測されるとのことで、台風を代表とする低気圧の接近などで体調を崩すいわゆる「気象病」をお持ちの方には悩みの種となります。
「気象病」の主たる症状は頭痛、めまい、倦怠(けんたい)感、関節痛、気分の落ち込みなどで、いわゆる自律神経の乱れがその病態の根幹です。一説には内耳内に気圧を感知するセンサーなるものが存在し、そのセンサーが気圧の変化を感知して、内耳内の圧変化によりめまい平衡を司る前庭神経が過剰興奮して自律神経の乱れに繋がるのではないかとも言われております。
耳鼻科領域でいうメニエール病や低音障害型難聴といった内耳の水腫(リンパ液が増えすぎて貯まる状態)に関しても気圧変化と症状悪化の関係性は半世紀以上前から報告されており、上述のような「気象病」と重複する病態があるのではないかと考えております。メニエールを含む内耳に関するめまい・耳鳴りと気象に関わる報告は多く、その症状悪化のメカニズムは大きく二つ、直接的か間接的かということで古くから議論があります。
直接的というのは気圧(外耳道圧)そのものが、中耳を介して内耳に圧変化を及ぼすというものです。ただ、気圧の変化から症状出現までは一般的にタイムラグ(9−22時間)があり、台風が近づいてきた翌日に起こるめまい・耳鳴りが多い点、また飛行機のような急激な圧変化で起こるめまいは珍しい点は報告されていますので、このような点を加味すると直接的な圧変化だけで病状が悪化するというのは、そのメカニズムの説明が難しい面もあります。
一方、間接的な内耳への圧変化のメカニズムについては、気圧変化に伴う体のホルモン分泌が介在して、その結果として内耳内の水腫が起こってしまうというものです。一例では、ストレスホルモンの一つで体内に水分を貯めようとするホルモン(抗利尿ホルモン:ADH)が内耳の水腫を引き起こすことが分かっており、もともとメニエール病の悪化にストレスは言われておりましたので、それを裏付けるメカニズムの一つとなりえます。その他、心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)という運動や頻脈などの心房に負担を与えることで血液中に増えるホルモンも内耳が水腫になる方向に働く可能性があるという知見も出てきており、運動や自律神経の調節障害等で循環動態に影響を及ぼした時にめまい・耳鳴りが生じうるメカニズムに関係している可能性もあります。ただ、ANPに関してはADHに拮抗(反対に作用)する動きもあるようで、ADHによる内耳の水腫を軽減する作用も報告されるなど、内耳に良い影響があるのかそれとも逆なのか、まだ不明な点が多いのが現状です。ただ、何かしら内耳のリンパ圧調節に関わっているようですので、いい影響があれば内耳の水腫改善薬の開発に繋がりますので、今後の研究成果が待たれるところです。いずれにせよ、内耳の圧変化にこれらのホルモン分泌が関わっているという説の場合、ホルモン分泌から内耳の水腫までには一定時間要しますので、症状出現までにタイムラグが生じうることも理にかなっており病態の理解としてはしっくりきます。
病態を知ることはもちろん予防に繋がります。抗利尿ホルモンは水分が体内に十分あれば分泌は抑えられますし、ストレス消化や自律神経のバランスを整えるためには睡眠や運動が効果的であることは古くから言われております。十分な水分摂取、適度に疲れてしっかり睡眠、健康維持において当たり前のことですが、台風などによるめまい・耳なりでお悩みの方は一度生活習慣を見直してみてはいかがでしょうか。
抗生剤使用と薬剤耐性のはざまで
花粉のシーズンが一段落したこの時期でも、鼻症状を訴える人は多く見受けます。寒暖差が多い日が続く影響もあり、自律神経や知覚神経による鼻炎(いわゆる寒暖差アレルギー)や薄着や寝冷えから風邪をひくことも多いかと思います。熱も喉も痛くないのに風邪?と思われるかもしれませんが、風邪はウィルスが原因で通常は鼻の粘膜から感染への免疫応答が始まるため、咽頭痛や発熱に先行して鼻汁が症状として出ることはあります。
風邪はウィルスと免疫の戦いですので、ほとんどの方が既感染で免疫を獲得しており通常は何もしなくても自身の免疫で治っていきます。通常は3日目をピークに症状が改善していき、終盤には鼻粘膜の修復過程でもたらされる粘り気のある鼻汁が出てきますが、これもまた自己治癒過程の一つです。鼻症状が5日目以降も続く場合がありますが、そのほとんどはウィルス感染後の急性副鼻腔炎で、風邪と同じく自身の免疫で自然治癒してきます。こじれて細菌による急性副鼻腔炎に移行する方もいますが、その率は低く過去の報告では風邪をひいた人の0.5-2%程度とされております。
これらの報告結果と昨今の薬剤耐性(AMR:Antimicrobial Resistance)対策からの抗生剤の適正使用の観点から、急性副鼻腔炎に対する抗生剤の使用は可能な限り制限するようにというのが世界的に同意を得た治療方針です。もちろん、重症細菌感染症へ移行しては困りますので、適切な抗生剤使用は時に必要です。ただ、小児の急性副鼻腔炎においては、最も重い合併症である頭蓋内感染の原因が主として薬剤耐性菌であるというデータもあり、これは抗生剤の不適正使用が最重症細菌感染症を招いてしまうという皮肉な結果ですので、抗生剤を漫然と使用することのリスクを示しています。
耳鼻科領域を超えてAMRの問題は看過できないレベルまで来ており、このまま抗生剤の乱用が続けば2050年には薬剤耐性菌の感染症で亡くなる人数が癌で亡くなる人数を上回るという試算もあり、世界的に取り込む喫緊の課題であるのは事実です。ですので、抗生剤の漫然とした処方は避けなければなりませんが、慢性の副鼻腔炎や小児に多い慢性の滲出性中耳炎にはクラリスロマイシンやエリスロマイシンといったマクロライド系抗生物質(ML薬)という細菌の増殖を抑える抗生剤を少ない量で長期間内服するのが有効なのも事実です。ただ、いくら長期とはいえ、さすがに延々と飲み続けるわけにもいきません。過去の報告で10週続けても6ヶ月続けても効果が同等であったということから、従来3ヶ月での効果判定が推奨されてきました。有効であれば6ヶ月までの内服継続は検討されますが、AMRの観点からも効果がない場合は治療方針の転換が必要で、手術療法(鼻の内視鏡手術、小児であれば鼻の奥の扁桃腺であるアデノイドの切除)も選択肢の一つに上がると考えます。
最後に、このML薬に関する知見を一つ。ML薬はその抗菌作用よりも免疫調整や抗炎症作用に首座をおいて、前述のように長期投与されることが多いのですが、この免疫調整や抗炎症作用の新たなメカニズムが近年の研究で明らかになっております。このことによりML薬の免疫調整や抗炎症作用生体に限定した新薬開発が期待されるということで、ML薬が大量に使用されている現状を打破しAMR対策に貢献すると考えられます。AMRは細菌の進化そのもので、たとえ乱用がなくなっても細菌自身は生存のため改変していきます。乱用の是正で改変スピードを一旦遅らすことができても、新薬がなければいずれ人類は改変した細菌により多くの犠牲を出すことになります。新薬開発に期待しつつ、抗生剤の適正使用に努めていきたいと思います。
鼻の神経応答ー鼻づまりは健康に必要かー
寒い時期が続く中、鼻症状でお悩みの方が多い印象です。この時期のアレルギーは何ですか?とよく聞かれますが、スギやハンノキの花粉が軽度飛散しそちらに反応していることもありますが、ウィルス感染による感冒症状やそれによる副鼻腔炎が主だっていることもありますので、鼻や喉の粘膜の状態を観察して適切な投薬となるよう心がけております。
鼻炎の診断をするにあたって視診は欠かせないのですが、中には鼻炎症状の訴えの割には診察時には比較的綺麗な粘膜の方や萎縮といったアレルギーや感染とも異なる粘膜の方もおられます。こういったアレルギーでもなく感染でもない鼻炎のメカニズムには神経反射の関与が言われており、寒いところで鼻水がよく出るといった寒暖差アレルギーといった血管運動性鼻炎や食事の時に鼻水や鼻詰まりが起こる味覚性鼻炎などが挙げられます。寒暖差があると自律神経の乱れが生じますし、食事の唾液分泌も自律神経が担っておりますので、いわゆる自律神経系の鼻炎とも言われてきました。ではなぜ自律神経が鼻の詰まりに影響するのかというと、自律神経は血管を縮めたりや広げたりしており、鼻粘膜の下には多くの細かい血管が存在するため、血管が縮んでいる時は粘膜が縮むので鼻は通り、血管が広がっている時は粘膜が腫れて鼻詰まりを生じてしまうということになります。
自律神経以外に寒さ刺激や辛さ刺激を司る知覚神経も、血管を広げる物質を放出することもわかっており、寒さ刺激や辛いものを食べた時に鼻水や鼻詰まりが起こるのは自律神経や知覚神経の複合的な要素で起こるのではないかと考えられます。こういった神経の反応と鼻症状の関係を示した興味深い研究の一つに、足湯によって鼻症状の緩和が見られたという報告があります。足湯ということで、いかにも温泉大国日本からの報告なのですが、足の温度が上がると鼻の粘膜の温度も上がるという神経反応があり、それにより鼻症状が改善する可能性を示したものです。鼻炎でお悩みの方は一度試されてみては如何でしょうか。
自律神経と鼻詰まりに関して、最近の知見をもう一つ。自律神経が鼻に影響を与えている生理反応の一種にnasal cycleというものがあります。片方の鼻が広がればもう片方の鼻は縮まるというものです。片鼻が詰まるのは病気ではないのか?ということで日本では交代性鼻炎と呼ばれているのですが、自律神経のバランスが取れている証拠の一つであり、もちろん病気ではありません。このnasal cycleの目的は鼻を片方ずつ休ませるなど諸説ありましたが、2021年にイギリスから新説が提唱され、その内容はnasal cycleが感染防御に対する役割を担っているというものです。元来、気道感染を起こすウィルスは32℃でよく増殖し37℃で増殖が抑えられることは知られていたのですが、鼻呼吸をする過程でnasal cycleにより片方の鼻が詰まる状況を作ることで咽頭部での加温が維持されウィルスが増殖しにくい状況を作っているというわけです。加湿下でもウィルスの増殖は抑えられますので、鼻の加温・加湿機能というのが生態防御の観点からは重要な働きをしているということです。
このことは手術をする側からも留意しなければならない点です。口呼吸が続くようなひどい鼻詰まりで、投薬でのコントロールが困難な場合は鼻腔形態を改善する手術も考慮しなければなりません。ただ上述の観点から鼻腔形態改善術においては、鼻の通りだけを念頭に置くのではなく、加温加湿機能を考慮した手術が大切であるということです。当院でもその点に注意を払い手術を行なっております。
隠れた難聴とその正体
「ウォークマン®︎(SONY)」を始めとした携帯音楽プレーヤが普及したのが20世紀後半、そして21世紀に入ってからの「iPhone ®︎(Apple)」の登場で一気にスマホが広がりこの30年で人はいつでもどこでも音楽と会話が楽しめるようになりました。ただ、このことは聞こえを司る聴器からすれば、音が長時間入ってきたり、強大な音に晒されたりと負荷が増えたことになります。特に近年、Bluetooth技術によるワイヤレスのイヤフォンの普及で若年者を中心にほぼ1日中、イヤフォンをつけているケースもあるようで、音響暴露によって難聴・耳鳴りを呈するいわゆる「スマホ難聴」が世界レベルで問題となっています。
「別に聞こえているし、ほっといてください」と若者にチクっと言われそうですが、強大音の長時間にわたる音響暴露が難聴や耳鳴を引き起こすことは既に明らかになっており、2018年にはWHOからも、若者11億人(世界の若者の約半数)が音響による聴力障害のリスクに晒されているとして緊急提言が出されております。この聴力障害は、従来の騒音性難聴(強大音により聞こえの感覚細胞がダメージを受けて難聴と耳鳴りが残ってしまう状態)だけを指すのではなく「大きい音を聞いて一時耳がおかしくなったがまた元に戻った」という状態も含まれております。後者のその状態は「Cochlea Synaptopathy」と呼ばれており、近年の研究からその病態は感覚細胞と神経繊維をつなぐ部分であるシナプスが障害されている状態であることが解明されております。
この「Cochlear Synaptopathy」ですが、厄介なのはこのシナプスの80%が障害されるまでは聴力検査(聞こえたらボタンを押す一般的な聴力検査)では異常を認めない点で、50%程度のシナプス障害では検査上は異常なしと流されてしまうところです。ゆえに難聴があるにも関わらず「難聴なし」とされてしまう難聴、いわゆる「hidden hearing loss(隠れ難聴)」の病態と言われているのですが、ここでいうシナプスの減少は詳細な聞き取りにも関与していることが分かっており、静かなところでの会話や聴力検査は問題ないが、雑音があると「言葉の聞き取り」が極端に悪くなるという訴えの背景にもこの「Cochlear Synaptopathy」があると言われております。また耳鳴りはこのシナプスの減少で生じ得ますので、「難聴を認めない耳鳴」としてもこの病態は注目されております。
加えて、一般的な難聴である「加齢による難聴」も「Cochlear Synaptopathy」同様なシナプス障害が主となって起こっていることが分かってきており、長年よる音響暴露の蓄積を経てシナプス障害が進んだ結果が加齢性難聴となることも言われております。事実、聴器の加齢性変化は既に20代よりゆっくり始まり、聴力検査で測り得ない高周波数領域より難聴が進んでいくと言われております。ただこの高周波数領域は日常生活音域ではないため、普段は難聴を意識しないわけですが、この状態も正確には「hidden hearing loss」となり、耳鳴り伴っている場合はやはり「難聴を認めない耳鳴」の一因となり得ます。
音響暴露の一つの目安ですが、WHOは大人で80dB,子供で75dBの音量を週40時間以上聴き続けると音響外傷のリスクがあると示しています。80dBの目安は地下鉄走行中の車内にいるときに感じる音量です。一旦失われた聴器の感覚細胞は元には戻りませんが、受傷直後であれば神経系の機能は休むことで回復することも事実ですので、休憩を入れ神経(シナプス)を回復させることも大切な予防です。耳鼻科の学会が掲げる標語の一つにHear well, Enjoy life.(快調で人生を楽しく)というのがあります。今後の人生のためにも、今ある聴力を大切にしましょう。
その副鼻腔炎 急性ですか?慢性ですか?
新型コロナが5類感染症に移行されました。パンデミック前の日常を取り戻しつつありますが、新型コロナとの共存は続きますので、怖がり過ぎず、甘く見過ぎず、適切な感染対策を実施していきたいと考えています。ウィルスとの共存という意味では、この時期(春から夏にかけて)はライノウィルスなど鼻炎を引き起こすウィルスが流行し、季節性アレルギー性鼻炎(いわゆる花粉症)とも重なり、鼻炎で悩む方が多くなります。鼻炎がこじれて副鼻腔炎を引き起こす方も多く、副鼻腔炎に至ると鼻周囲や額の痛みも伴ってきますので日常的には鼻炎よりさらに辛い状況となります。
副鼻腔炎には急性と慢性があり、急性は感染による鼻炎が引き金となっておりそのほとんどが風邪(ウィルス)からの移行と言われております。慢性については、急性を繰り返すものが慢性と従来考えられてきましたが、現在は急性の反復という病態は、慢性とは病態が異なるゆえに分けて考えるのが正しいとされています。では、副鼻腔炎の慢性とは?という事ですが、その病態は急性のような持続感染があるのではなく、免疫応答異常などの持続炎症がある状態と理解されています。ややこしいですが、簡潔に言えば、急性は感染が主体、慢性は感染が主体ではないということです。
このことは、治療法に反映されます。急性は感染ですがウィルス感染が主で、抗生物質が必要な細菌感染に発展するのは2%程度と言われています。ですので、急性の治療で積極的に抗生剤を使用するのは基本的には推奨されておりません。ただし、状況に応じて抗生剤を使用しなければ眼や頭に炎症が波及するようなよりひどい状況にもなってしまいますので、ガイドライン(IDSA:米国感染症学会など)に則って適宜必要と判断した際には抗生剤を使用しないといけません。慢性においては、その背景は感染主体ではありませんので抗生剤は基本的に必要ないことになります。ただ、細菌を殺す「殺菌的」なものとは別の細菌の増殖を抑える「非殺菌的=静菌的」な抗生剤であるマクロライド系抗生剤(ML)はよく使われます。これはMLの抗菌作用以外の抗炎症作用に期待した治療で、慢性の病態が持続炎症であることを考えれば理にかなっており、少量で長期間投与することで効果も示されております。現時点では副作用も少なく有効な治療と考えられていますが、投薬はあくまでも全身投与ですので長期投与となると薬剤耐性(抗生剤が効かない細菌の出現)の問題や全身への影響(肝機能障害など)に気を配らなければなりません。
慢性の治療について最近のトピックスを少し。慢性の病態が持続炎症であるという観点から、抗炎症作用がありかつ局所投与で安全性の高いステロイドの噴霧にスポットが当たっております。従来の鼻の噴霧ステロイドは、その成分の5%以下しか副鼻腔炎の炎症部に到達せず、その薬剤到達法が課題でした。そのことを改善すべく、米国では呼吸補助下での鼻のステロイド噴霧(XHANCE®️)が開発され、より鼻腔の深部まで有効成分を到達させることに成功しております。国内においても喘息用の吸入式噴霧ステロイドを口から吸って鼻から出すという「経鼻呼出療法」が慢性副鼻腔の治療にも応用されております。慢性でもより重い好酸球性副鼻腔炎に対してですが、症状改善に有効であると報告されております。当院でもできるだけ有効な点鼻吸入指導をして、症状の改善に努めております。
聞こえと認知症の深い関係
「人生100年時代」・・半世紀前には考えられなかったような言葉が使われている現在、公衆衛生をはじめ医学の進歩の恩恵で人類は平均寿命を大きく伸ばしてきました。高齢期の健康状態を維持しようという概念のもと、WHOが2000年に提唱した「健康寿命」という言葉も今やすっかり定着しております。この「健康寿命」とは平均寿命から認知症など継続する介護状態の期間を引いたもので、最近のデータで、平均寿命が男性約81歳女性約88歳(2021年)に対して、「健康寿命」は男性約73歳女性約75歳(2019年)となっております。
できれば認知症など介護が必要な状態にならないよう努めたいところですが、それでも寿命が伸びるに伴い認知症患者の数も増えてきており、国内において2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になると予測されております。こうみると加齢による認知症のリスクは避けて通れずと言ったところです。とはいえ出来るだけリスクを回避できるようにするのが医学の務めであり、有力医学誌においても近年「認知症のリスク因子」が報告されております。その報告からは、現時点で分かりうる危険因子が時期別(若年期・中年期・高年期)に考察されており、危険因子が高い順に「中年期の難聴」・「若年期の低教育」・「高年期の喫煙」・「高年期の社会的孤立」ならびに「高年期のうつ」となっております。この報告からは、関連性は一見薄いように思いますが、最大の危険因子は難聴ということになり、そのほかの報告からも同様に、難聴を放置することは認知機能の低下につながることや、その裏返しで、適切な難聴の治療が認知症の予防につながる可能性が言われております。さらに難聴になると他者とのコミュニケーションが取りづらくなり、認知症の危険因子である「社会的孤立」を引き起こし、それがまた「うつ」につながりさらに認知症になるリスクを上げると考えられております。
年齢による難聴(加齢性難聴)は遺伝的要素があり個人差はあるものの、聞こえを司る細胞は生まれた時から歳を重ねるごとにその数は低下の一途をたどるため、何らかの難聴は早ければ50代から始まり70代では約半数の人に現れると言われています。年齢には抗えないとはいえ、環境因子が難聴悪化に関係している事は古くから言われており、半世紀以上前のレポートですが、アフリカの無音静寂下に暮らす部族の聴力を調べた結果、年齢を重ねても難聴はほとんど進行していないとする報告があります。彼らの血圧もまた高齢に至っても上がらなかったようで、このことから、騒音や高血圧を放置することで起こる動脈硬化などが加齢性難聴の悪化に関連していると言われております。近年ではもう少しミクロのレベルで解析され、騒音による「酸化ストレス」や動脈硬化による「微小血流障害」が耳の奥にある聴覚を司る細胞を傷つけていくことで難聴が進行していくという説が有力です。
いかんせん、年齢による変化で一旦機能を失った聴覚細胞は元に戻らないのが現状です。その聴力を改善する方法は、より重度であれば人工内耳などの手術もありますが通常は集音器や補聴器ということになります。近年は集音器の質も向上しており、一般家電量販店で入手可能で試す価値は十分にありますが、より高度なものとなるとやはり補聴器となります。補聴器は個々に合わせて作成するためより高い技術を要しますので、補聴器作成は認定補聴器技能者のもとで作成することを推奨します。当院でも専用の補聴器外来を設けており、認定補聴器技能者のもとでの補聴器作成とアフターケアを行なっております。また認定補聴器技能者のいる補聴器販売施設への紹介もしておりますで、補聴器を作りたいと思われる方は一度ご相談ください。
コロナ感染のち、舌の異常
コロナ感染(COVID-19)が世に出て2年半が経ちました。ウィルスの変異は続くものの、その特性は概ね把握されつつあるのか欧米では共存・共生の生活様式が定着し諸規制が撤廃されつつあり、日本にもその流れが届きつつあります。国内での規制緩和にはまだ議論があるでしょうが、感染し回復された方も散見されてきており、このウィルスが「common disease(一般的な病気)」となり「common cold(風邪)」に近づきつつあるのかもしれません。ただ、インフルエンザのような専用治療薬が汎用化していない以上は高齢者や免疫弱者は重症化の危険を伴いますので、引き続き感染予防に努めることは大切です。
患者さんの中にもコロナウィルスに感染してからの不調を訴える方も増えてきており、その中でも特に舌の異常である「味覚異常」と「舌の違和感」を訴える方が多い印象です。
「味覚異常」は舌そのものの味覚を司る細胞がやられてしまうこともありますが、嗅覚が障害を受けて味覚が鈍ってしまうということもあります。味の決定は実は嗅覚に頼っているところが多く特に口から鼻に戻ってくる風味がなくなると味がおかしいと錯覚してしまうとも言われております。人が鼻呼吸であることを考えると、飛沫によりまず鼻で感染がおこり、ウィルスによる嗅覚障害が先行して味覚が鈍っていることも味覚異常の原因として重要です。また、コロナ等ウィルス感染は全身疾患ですので倦怠感や食欲不振で低栄養が続くこともあります。このことが必要微量元素の一つである亜鉛の不足をもたらし、これが味覚障害につながることもありますので、感染後より食が細くなった方は亜鉛不足も考えなければなりません。
「舌の違和感」というのは、細かく聞くと「味覚はあるが舌が何かおかしい」または「舌が痛い・ピリピリする」という訴えで来られることが多い印象です。病み上がりという言葉があるように感染後は免疫が正常化しておらず違うウィルスに感染したり細菌による混合感染を引き起こしたりしやすいですのでそこで真菌(カビ)などの通常の免疫ではかかりにくいような舌の感染症を引き起こしてしまう可能性もあります。さらには舌全体が焼けるように痛くなる口腔内灼熱症候群(Burning Mouth Syndrome)やその一つのタイプとされている舌痛症がコロナ感染をきたした患者さんによく見られているという報告も最近上がってきております。これらは脳や脊髄に原因がある顔面痛の一種で、舌に痛みをきたしうる様々な病気がないことで診断される病気です。言いかえれば、病態として不確定なことが多く心身症的な側面があるのですが、ウィルス感染後に抑うつや精神不安を訴える方も多く、舌の違和感に何らかの影響をきたしている可能性は高いと考えられます。
これら舌の異常はウィルス感染全般に共通することでもあり、コロナパンデミックが世に出る前にもそのメカニズムは言われておりました。ただ、コロナ感染でより多く事例が上がってきていることはこのウィルスの感染力や重症化のリスクが従来の風邪ウィルスより高いから、すなわち人類が新たなウィルスに対して免疫を持っていないことが要因なのでしょう。しかし、共存するために新たな免疫を獲得し、それによる後遺症についても一つ一つ紐解いていかなければ前へは進めません。新たな知見に期待しつつ可能な限り臨床の現場で生かせていければと考えております。
耳の不調と睡眠
コロナパンデミックの中、ライフスタイルも変化し屋内時間が増えるなどして生活のリズムが変わった方も多くおられると思います。生活リズムが変わり在宅ワークが増えるなどすると遅寝遅起きの習慣から睡眠のリズムも変化し、それによる体調不良などを訴える方も日常診療の中で少なくない印象です。
耳鼻科領域での体調不良の一つにめまい・ふらつきがあり、特に平衡機能障害と睡眠の不調の関係は近年注目を集めております。というのも耳鼻科受診しためまい患者さんの60%以上が何らかの睡眠障害を持っているとの報告もあり、睡眠が平衡機能の維持にいかに深く関与しているかが伺えます。事実、脳幹にある睡眠と覚醒を司っている部位には耳の平衡を司る三半規管からの神経信号が入っていることが分かっており、「平衡の不調」が「睡眠の不調」に繋がる可能性が指摘されています。具体的には、三半規管のめまい疾患の有名な一つ、メニエール病を患っている患者さんを睡眠検査したところ、正常の方と比べて深い睡眠(いわゆる熟睡)が欠落していることが分かっており、その可能性を裏付けるデータとなっております。逆に、「睡眠の不調」が「平衡の不調」をきたすこともあり、具体的には、睡眠障害の一種である睡眠時無呼吸症候群の診断を受けた患者さんが、慢性的な低酸素状態が続くことで中枢(脳)の不調や末梢(三半規管)の不調をきたし平衡機能の障害を伴うことも近年開発された精細なめまい検査の解析から判明してきております。
もう一つ、耳鼻科外来でよく遭遇する睡眠障害関連疾患に耳鳴りがあります。概ねの訴えは「耳鳴りのせいで眠れない・・」というものですが、耳鳴りはその原因が中耳炎など治療可能な病気によっては消失させることも可能ですが、多くは神経レベルの難聴など根本治療が困難な疾患が背景にありますので完全消失は困難です。それゆえに付き合っていく、鳴っているけど気にならなくしていくという考え方が大事なのですが、睡眠障害があるとそもそもその考え方に達することが困難となります。正解は、「耳鳴りのせいで眠れない」のではなく、「眠れないので耳鳴りが大きくなる」となりますので、まずは不眠治療に専念すると言うことになります。
睡眠障害の治療ですが、現在はその専門である日本睡眠学会から一定の治療基準も示されております。2013年の国際基準で睡眠障害の原因は大きく7つに分類(原発性不眠症・睡眠呼吸障害・概日リズム調節障害・むずむず足症候群・睡眠時随伴症・過眠症・睡眠衛生不良)されており、治療の第一は睡眠薬の使用ではなく、その原因をしっかり見据えた上での睡眠衛生指導といういわゆる生活指導的な治療となっています。投薬が必要な場合も第一選択は非ベンゾジアゼピン系という、従来日本で大量に使用されてきたベンゾジアゼピン系ではない投薬となります。この背景には、いまだ日本で多く処方されているベンゾジアゼピン系睡眠剤の依存性の問題や体内時計を狂わす懸念や認知症リスクを高める懸念があるものと考えられます。近年は、従来の睡眠剤とは異なる「自然な眠りを誘導する睡眠剤」も出てきており、治療薬の幅も増えてきておりますので、睡眠剤の適正かつより計画的な使用により睡眠障害が改善されることが示されております。
睡眠障害はその影響が全身に及びます。耳鼻科領域においても、特にめまい・耳鳴と睡眠障害が併存しているケースでは睡眠障害の鑑別は治療方針の要ですので、睡眠障害を専門とする医師との連携のもと適切な治療を行うことが症状改善に繋がると考えております。
閉じない耳管、開かない耳管
『未知の臓器が喉の奥から発見!』とネットニュースにもなりましたが、2020年にオランダのがん研究施設のチームが喉の奥ではなく鼻の奥の耳管という耳と鼻を繋ぐ管の周囲に新たな分泌腺(唾液腺?)が存在していると発表しました。今までの解剖学の教科書にも記載されていない知見であり、鼻の奥の湿潤や嚥下に関わっているのではと推測され、さらには耳管機能障害などの病態にも関わっている可能性もあるとのことです。
耳管機能障害とは鼓膜の奥の中耳の圧交換を担っている耳管がうまく働かず、中耳の圧を一定に保てない状況に陥ることです。通常耳管は閉じており嚥下(飲み込む)時に開き圧交換が行われるのですが、うまく働かない病態として嚥下時に開きにくくなっている状態(耳管狭窄症)ないしずっと開いたままで閉じない状態(耳管開放症)が挙げられます。耳管狭窄症の原因は鼻の奥に腫瘍や顕著な後鼻漏(鼻の奥への鼻汁の垂れ込み)・炎症が存在することで、具体的にはアデノイドという鼻の奥の扁桃組織や副鼻腔炎・アレルギーによる慢性炎症によるところが大きく、アデノイド切除や内服による消炎で治癒することが見込めます。それに対して耳管開放症はその原因が耳管周囲の脂肪減少や血流低下によるところが大きいとされ、体重減少や妊娠に伴って発症しやすいと言われています。加えて、耳管開放が重度だとなかなか戻りにくく、完治に至りにくい病気です。
加えて耳管開放症は、完治しにくいがゆえに症状などの持続によって二次被害をもたらしてしまいます。その一つは「自声響音」といって自身の声が耳管開放のある側の耳に響いてしまう状態で、この症状が持続すると喋る度に声が響くために喋りづらくなり、重度の場合は会話がつらくなり引きこもりや鬱へと繋がる可能性もあります。他に、症状ではないのですが耳管開放症の方に多く見られる「鼻すすりの習癖」というのも二次被害をもたらします。鼻をすすることで耳管は閉じる状態に向かうため、耳管開放症の方はよく無意識に鼻すすりを行ってしまいます。鼻をすする行為は中耳の圧を陰圧にする(圧を抜いてしまう)行為になりますので、継続的な鼻すすりは中耳の慢性的な陰圧状態を生んでしまいます。この状態が続けば鼓膜が凹んだり癒着したりする中耳炎(癒着性中耳炎や真珠腫性中耳炎)となり、手術以外では治癒しない病態を作ってしまいます。
このような厄介な耳管開放症ですが、全く治療法がないわけではありません。内服で耳管周囲の血流を増やして耳管粘膜を膨張させる方法、鼓膜にチューブ留置を行い中耳の圧を抜くことで鼓膜の凹みを避けたり自身の声の反響を和らげる方法などがあります。ただ、これらの方法でも約5割の人にしか治療効果はないという現状であり、まだまだ完治困難な病気ですが、新たな治療法の開発も期待されております。最近では「耳管ピン」というシリコン性のピンを鼓膜経由で開放耳管に挿入することで、症状を緩和させる手術加療が国内で保険適応になっております。適応は重症耳管開放症の方ですが、従来の治療で効果の薄い方の一助となることが期待されています。
適切な治療を行うにはまずは正確な耳管機能障害の診断が必要です。耳管機能検査機器は当院でも導入しており、より正確な耳管機能の評価を行っておりますので、耳管機能障害かもと思われる方は一度ご相談ください。